本日のニュースで米連邦準備制度理事会(FRB)が、政策金利を0.75%上げることを決定しました。
記録的な物価の上昇が続いています。この物価の上昇を抑えるために上げ幅を従来の3倍にしました。
物価の上昇、つまりインフレーションを抑制させるためになぜ、利上げをするのか?
今回はこの仕組みについてまとめました。
インフレーションとは
そもそも、インフレーションとはどういうことでしょうか?
インフレーションは物価が上がること。例えば$1で売っていたモノの値段が$2に上がることです。
つまり、$1の価値がもともとは商品1個を買うことができる価値だったのに、物価が上がることで商品を半分しか買うことができない価値に下がります。
アメリカ政府としては、インフレーションになることは、お金の価値が減ることになるので阻止したいです。
また、急激なインフレーションは、給料の上昇が追い付かないため、物価が上がることで今までと同じ生活が維持できない人も出てきます。
そこで、政府はインフレーションの対策として政策金利を引き上げて、民間の金融機関の預金金利や貸出金利が上がるようにします。
民間の金融機関の金利が上がるとどうなる?
政府が政策金利を上げたことで、民間の金融機関が金利を上げます。
金利が上がることで銀行からお金を借りて、新しい設備に投資したり、事業拡大を考えていた企業は、採算が取りにくくなり、そういった投資をしなくなります。
これによって、設備を売っている会社は買ってもらえなくなり、売り上げが下がることにもつながります。
つまり、金利が上がることでお金を借りてモノを買う人が少なくなり、ビジネスの動きが緩くなります。
また、銀行に預けた場合の金利も上がるので、使わないで銀行に預けておこうとする人も増えます。
みんなが消費を控えてモノが売れなくなると、企業は、他社との価格競争などを激化して、物価が下がり、インフレーションからデフレーション(物価の下降)になります。
インフレとデフレ
インフレーションが進むことで、政府はお金の価値が減るために、それを阻止するために利上げをして、インフレーションからデフレーションになることを目指します。
これだけを聞いてしまうと、インフレーションよりもデフレーションの方が良いと考える人もいますが、デフレーションが進み、モノの値段が低くなると、企業の収益が落ち込みます。
これによって、倒産や、給料のカットなども起きます。
つまり、インフレーションが進んでも、デフレーションが進んでも良くないということです。
インフレーションとデフレーションがどちらが良いかに関しては別の機会にまとめたいと思います。












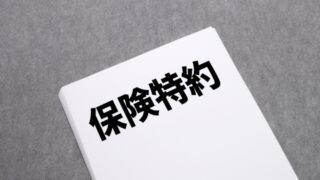








コメント